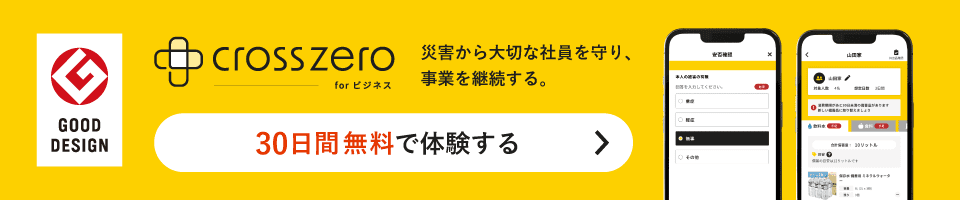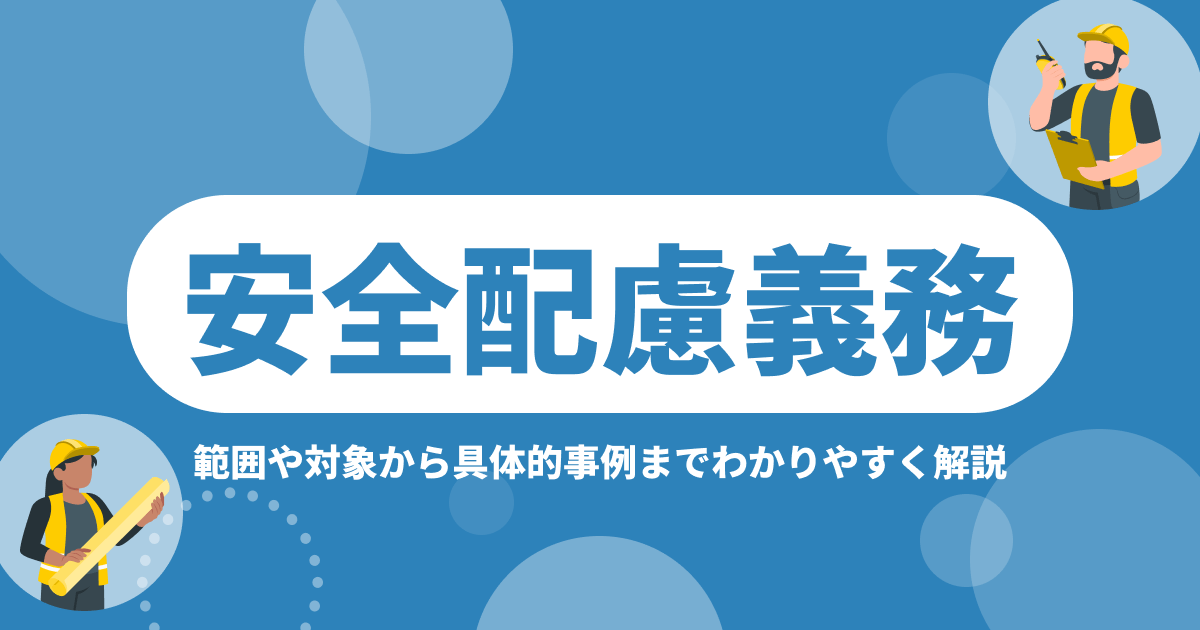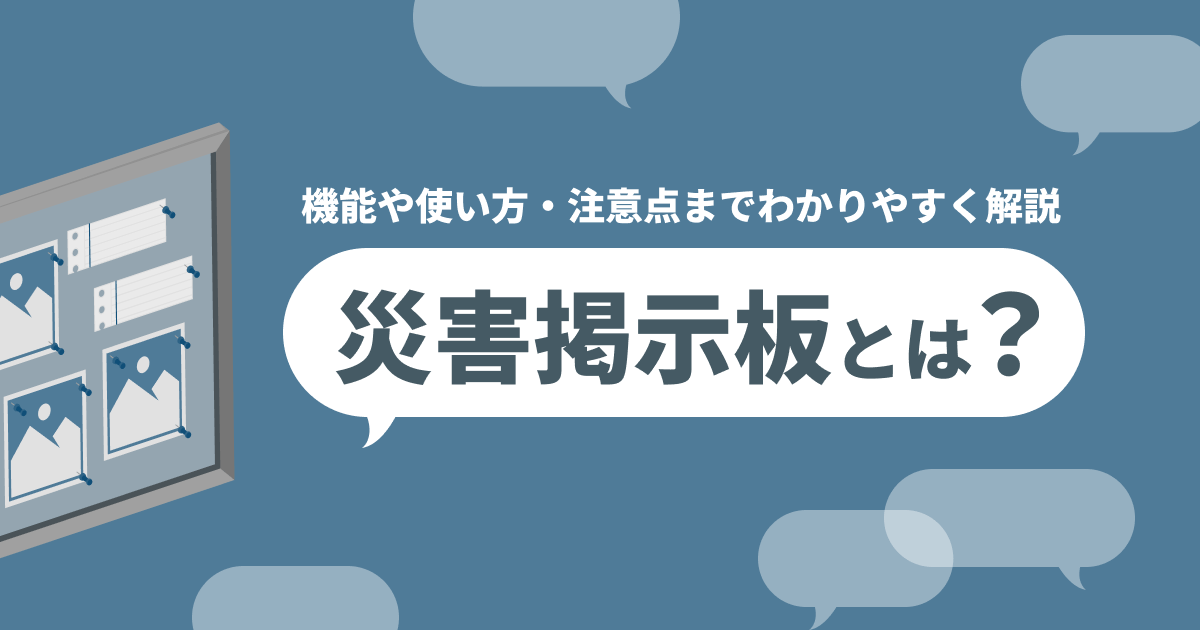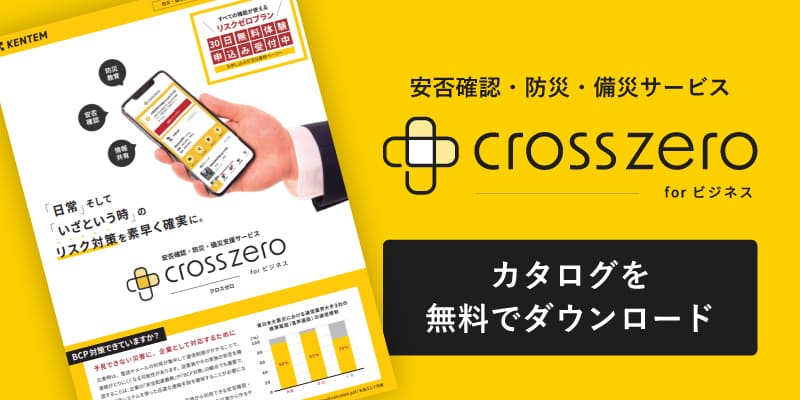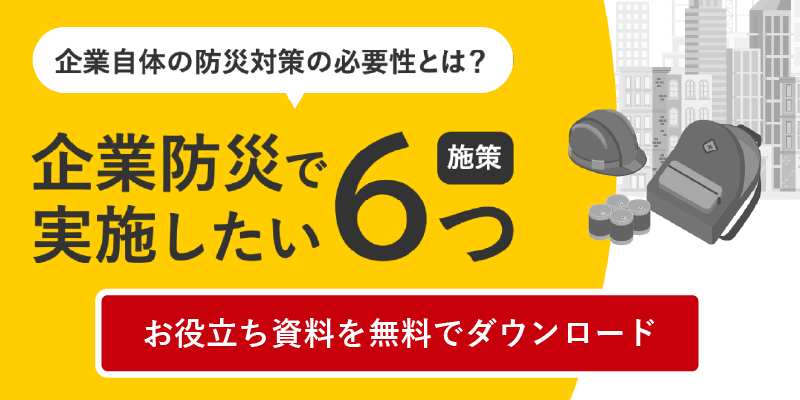生産性向上推進体制加算とは?算定要件や取得のポイントをわかりやすく解説
2025/03/25
令和6年度介護報酬改定により、新たに「生産性向上推進体制加算」が創設されました。
この加算は、ICT機器の活用による業務効率化と、介護サービスの質の向上を両立させることを目的としています。
加算(Ⅰ)では月額100単位、加算(Ⅱ)では月額10単位が算定でき、介護事業所の経営改善につながる制度と言えるでしょう。
本記事では、煩雑になりがちな算定要件をわかりやすく整理し、準備から申請までの具体的な手順をご紹介します。
テクノロジー導入による職員の負担軽減と、収益アップの実現に向けた実践的なポイントを解説します。加算取得をご検討の方は、ぜひ参考にしてください。
生産性向上推進体制加算とは?
令和6年度介護報酬改定で新設された生産性向上推進体制加算は、介護サービスの質を維持・向上させながら業務の効率化を図る取り組みを評価する加算制度です。
介護現場の人材不足や業務負担の増加などの課題に対応するため、ICT機器の活用や業務プロセスの見直しなどを通じた生産性向上の取り組みを推進します。
ここでは、制度の概要や新設に至った背景、そして対象となる介護サービスを詳しく解説していきます。
制度の概要
生産性向上推進体制加算とは、2024年度の介護報酬改定で新設された制度です。
本制度は以下の4つの実現を目的としています。
- 利用者の安全の確保
- 介護サービスの質の確保
- 職員の負担軽減
- ICT化の促進
この加算制度は、取り組みのレベルに応じて2つの区分が設定されています。
基本的な要件を満たす場合は月10単位を算定できる加算(Ⅱ)、より高度な取り組みを実施している場合は月100単位を算定できる加算(Ⅰ)が設けられています。
なお、加算(Ⅰ)は加算(Ⅱ)の上位制度となるため、同時に算定はできません。
参照:厚生労働省「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」
新設された背景
生産性向上推進体制加算が新設された背景の一つが、介護業界の人材不足です。
厚生労働省の「介護人材確保に向けた取組」によると、介護職員の必要数は2023年度の233万人から、2025年には243万人へと増加しています。
これは年間約5.3万人の介護職員の増加が必要となることを意味し、さらに2040年には280万人もの介護職員が必要になると試算されています。
一方で、日本の生産年齢人口は減少の一途をたどっているのが現状です。
2020年時点で7,509万人だった15歳~65歳の人口は、2040年には6,213万人にまで減少する見込みです。
少子高齢化や人口減少が進むなか、働き手の確保はますます困難になることが予想されます。
参照:厚生労働省「我が国の人口について」
このような状況を踏まえ、国と地域は介護職員の資質向上や労働環境・処遇の改善に取り組んでいます。
生産性向上推進体制加算は、この取り組みの一環として新設されました。
対象となる介護サービス
生産性向上推進体制加算の対象となる介護サービスは、主に以下の4つのカテゴリーに分類される16の施設種別です。
- 施設系サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院など)
- 短期入所系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護など)
- 居住系サービス(特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護など)
- 多機能系サービス(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など)
なお、本加算の対象は入所・居住系のサービスが中心となっていて、通所施設や訪問介護施設は対象外です。
サービス提供形態に応じて算定の可否が異なるため、自施設が対象となるか確認が必要です。
生産性向上推進体制加算の算定要件は?
生産性向上推進体制加算の算定には、以下のような要件の達成が求められます。
- 加算(Ⅱ)の算定要件
- 加算(Ⅰ)の算定要件
ここでは、それぞれの加算区分の具体的な算定要件を解説していきます。
加算(Ⅱ)の算定要件
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)は、介護現場の基礎的な生産性向上への取り組みを評価する区分です。
テクノロジーの活用と業務改善を通じて、職員の負担軽減とサービスの質の向上を目指します。
この加算区分では、最低1つのテクノロジー機器の導入が求められ、月額10単位が算定できます。
比較的取り組みやすい要件設定となっているため、まずはこちらから検討すると良いでしょう。
主な算定要件をまとめると、以下のとおりです。
委員会の設置 利用者の安全、サービスの質確保、職員の負担軽減に向けた委員会の開催と安全対策の実施 テクノロジー導入 1つ以上のテクノロジー機器(見守り機器やインカム、介護記録ソフトウェアなど)の導入 業務改善 生産性向上ガイドラインに基づいた取り組みの実施 データ提出 事業年度ごとの実績データを厚生労働省へ提出
なお、データ提出は、取り組みの効果を可視化し、継続的な改善につなげることを目的としています。
制度の活用にあたっては、自施設の現状を踏まえた計画的な準備が必要です。
加算(Ⅰ)の算定要件
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)は、より高度な生産性向上への取り組みを評価する区分で、月額100単位が算定できます。
加算(Ⅱ)の基本要件に加え、複数のテクノロジー機器の導入や役割分担の明確化など、より踏み込んだ取り組みが求められます。
基本的な算定要件をまとめると、以下のとおりです。
加算(Ⅱ)要件 加算(Ⅱ)のすべての要件を満たすこと テクノロジー導入 3種類すべての導入が必要(見守り機器・インカム・介護記録ソフトウェア) 役割分担 介護職員の専念時間の確保、介護助手の活用など データ提出 事業年度ごとの実績データを厚生労働省へ提出
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の取得には、段階的なアプローチが推奨されています。
多くの場合、まず加算(Ⅱ)を取得し、実績を積み重ねながら加算(Ⅰ)へ移行する流れとなります。
加算(Ⅱ)から加算(Ⅰ)への移行には、3ヶ月以上の取り組み実績と以下の効果実証が必要です。
- 利用者満足度の維持
- 総業務時間・超過勤務時間の短縮
- 年次有給休暇取得数の維持または増加
なお、新規に加算(Ⅰ)を取得する場合でも、同様の効果実証が求められます。
既に取り組みを実施している事業所は、利用者へのヒアリング調査などで代替することも可能です。
いずれの場合も、継続的な取り組みとその効果の可視化が必要です。
生産性向上推進体制加算を取得するための4つのポイント
ここでは、確実な加算取得に向けた4つのポイントは、以下のとおりです。
それぞれ詳しく説明します。
生産性向上委員会の設置
生産性向上推進体制加算を取得するためには「生産性向上委員会」を設置し、3カ月に1回以上の定期的な開催が必要です。
この委員会は、施設や事業所全体で生産性向上に取り組む中心的な役割を果たします。
具体的には、業務改善の課題を話し合いや解決策を検討・実行する場として機能し、職員全員が一体となって成果を目指すための体制づくりが求められます。
委員会は多職種からなるメンバーで構成しなければなりません。
具体的には、管理者だけではなく介護職員やユニットケアリーダーなど、現場の状況を直接把握できる職員の参画が必要です。
委員会での主な検討事項には、以下のようなものが挙げられます。
| 安全性とケアの質 | 利用者の安全確保とケアの質向上に関する取り組み |
|---|---|
| 職員への配慮 | 負担軽減策の検討と勤務状況の改善 |
| 機器管理 | 介護機器の定期点検と適切な運用 |
| 教育体制 | 職員への定期的な研修実施(特に加算(Ⅰ)では必須) |
なお、加算算定開始月より前に委員会を開催し、議事録などで活動実績を残しておく必要があります。
例えば4月からの算定を目指す場合は、それ以前に委員会を立ち上げ、具体的な活動を開始しておくことが求められます。
業務改善の成果を示すデータ提出
生産性向上推進体制加算の算定には、取り組みの効果を客観的に示すデータの提出が不可欠です。
特に加算(Ⅰ)では、具体的な業務改善の成果を数値で示す必要があります。
提出が必要なデータには、以下のようなものが挙げられます。
加算(Ⅱ)
- ア 利用者のQOL等の変化(WHO-5等)
- イ 総業務時間及び超過勤務時間の変化
- ウ 年次有給休暇の取得状況の変化
- エ 心理的負担の変化(SRS-18等)
- オ 機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)生産性向上推進体制加算Ⅱ上記のうちア~ウ
加算(Ⅰ) 加算(Ⅱ)のうちア~ウ
特に生産性向上推進体制加算Ⅰは、実際に業務改善の成果が現れていることが要件となります。
具体的には上記のデータでケアの質が維持または向上したうえで、職員の負担軽減が確認されることが必要です。
職員の負担軽減に関しては、労働時間の短縮や、有給休暇の取得日数の増加などで証明できます。
生産性向上ガイドラインの活用
生産性向上推進体制加算を算定する際には、生産性向上ガイドラインに基づいて業務改善のための取り組みを行うことが求められます。
このガイドラインは、厚生労働省が公開している生産性向上の取り組み手順やポイントをまとめた資料です。
施設系サービスと居宅系サービスそれぞれに専用のガイドラインが用意されています。
業務時間見える化ツールや課題把握ツールなどの使い方のほか、取り組みの評価方法や具体的な事例なども詳しく記載されています。
ガイドラインを効果的に活用すれば、より効率的な業務改善の取り組みが可能となります。
必須テクノロジーの導入
生産性向上推進体制加算の取得には、テクノロジー機器の導入が必須要件となります。
加算(Ⅱ)では1種類以上、加算(Ⅰ)では以下の3種類すべての導入が必要です。
| テクノロジー機器 | 主な効果 |
|---|---|
| 見守り機器 |
|
| インカムなどの通信機器 |
|
| 介護記録ソフトウェア |
|
特にインカムやチャットツールの選定は、加算取得の成否を左右するポイントとなります。導入に際しては、以下の点に注意が必要です。
- 介護現場での使いやすさ
- 確実な情報伝達
- 緊急時の即時対応
- 記録の保存と確認機能
まとめ
生産性向上推進体制加算は、令和6年度の介護報酬改定で新設された制度です。
介護現場での人材不足の課題に対し、テクノロジーの活用と業務改善を通じて、サービスの質を維持・向上させながら職員の負担軽減を目指します。
加算の取得には、生産性向上委員会の設置やデータの提出、ガイドラインに基づいた取り組みなど、いくつかのステップが必要となります。
特に重要となるのがテクノロジーの導入です。
見守り機器やインカム、介護記録ソフトウェアなど、現場のニーズに合わせた適切な機器選定が求められます。
総合防災アプリ「クロスゼロ」は、チャット機能による円滑な情報共有はもちろん、BCP(事業継続計画)策定支援や災害時の安否確認機能など、介護・福祉事業所に必要な機能を総合的に提供してくれます。
加算取得のためのテクノロジー導入と、事業所の安全・安心な運営の両立を実現する強力なツールとして、ぜひご検討ください。