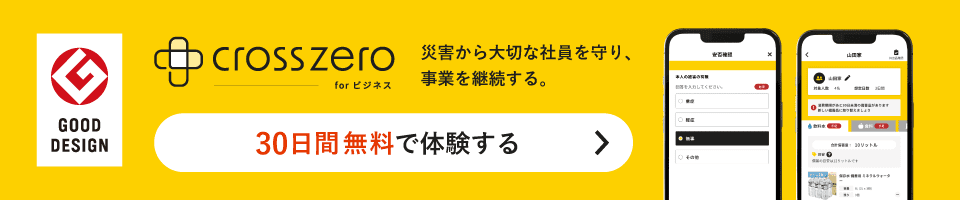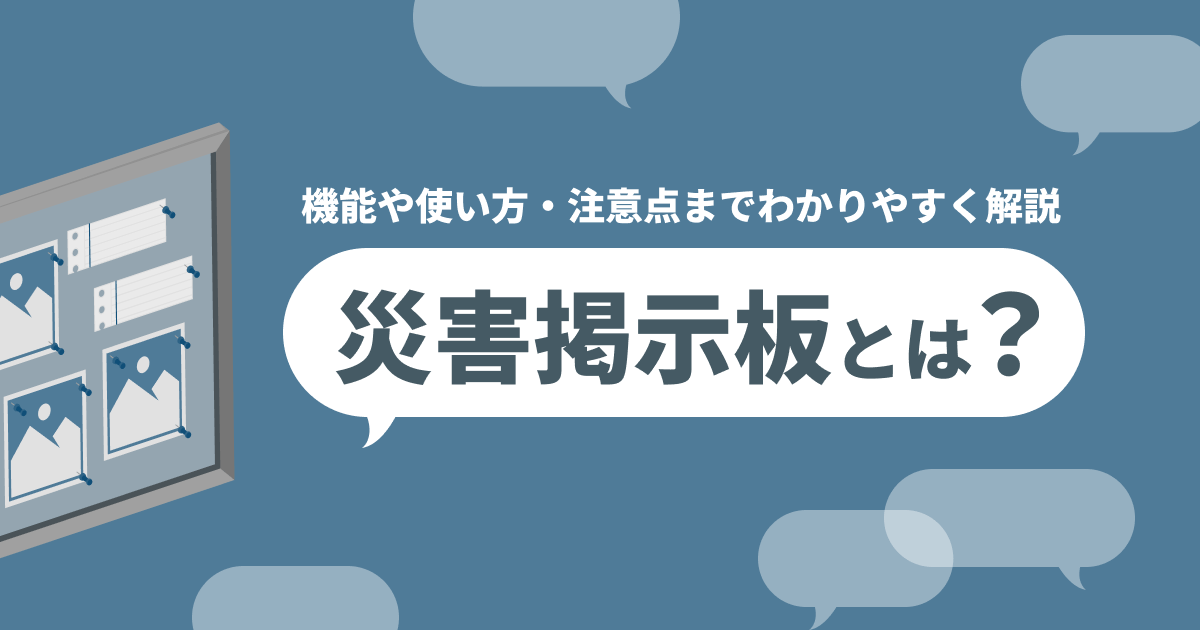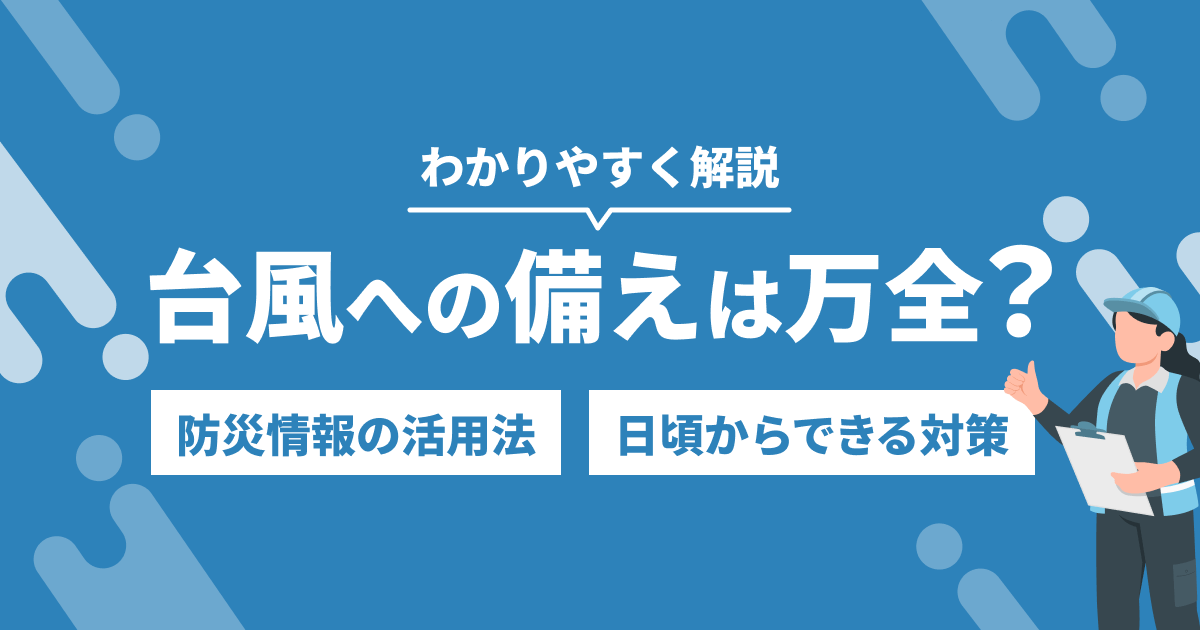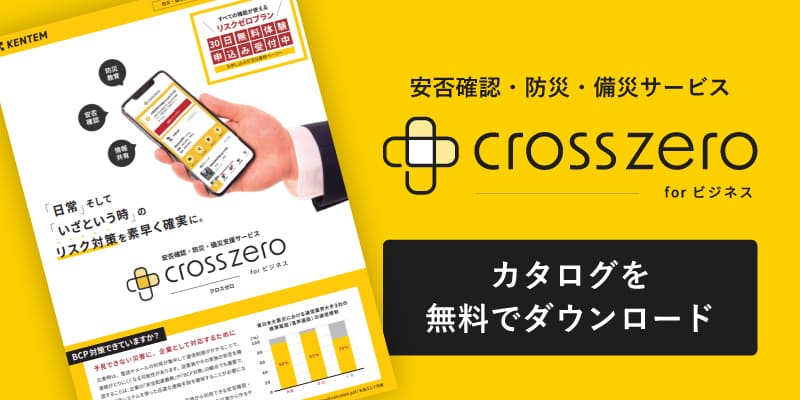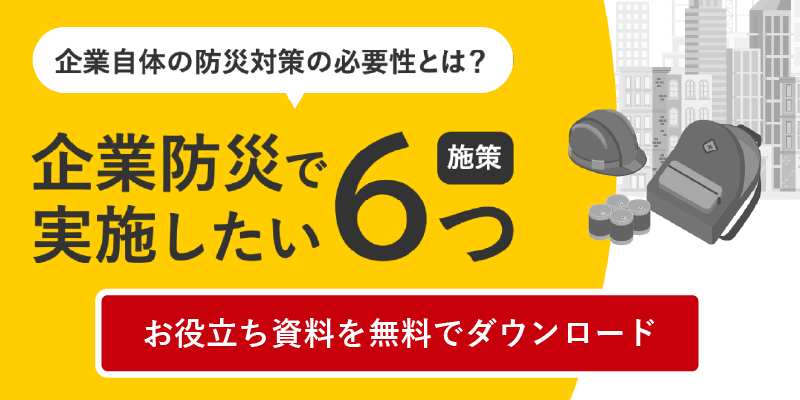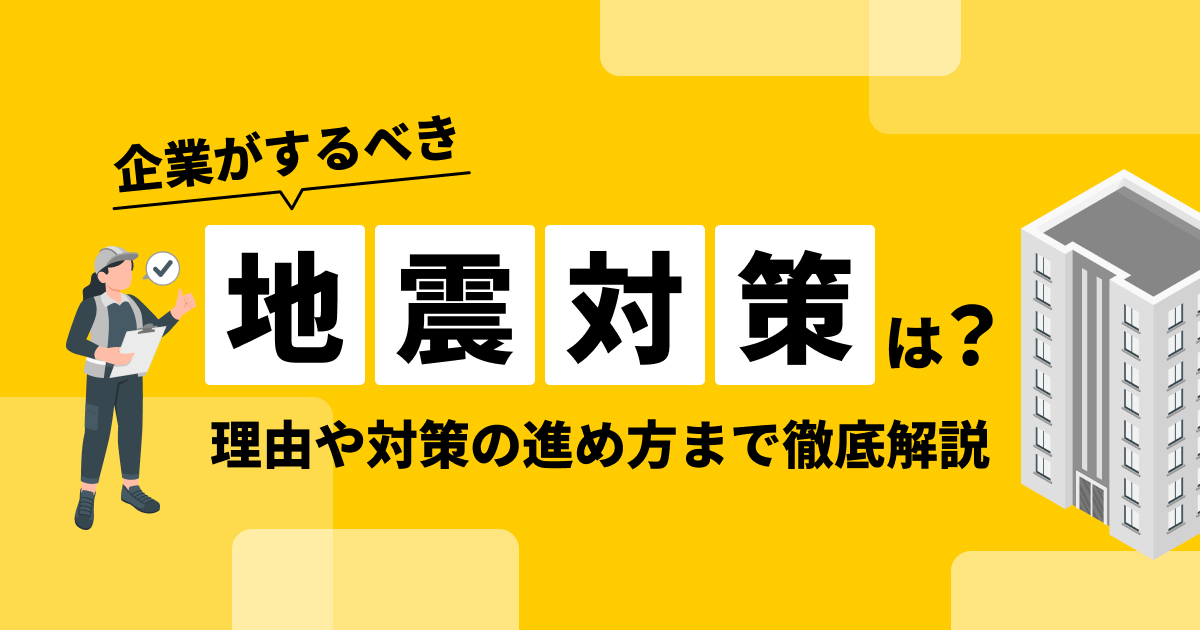
企業がするべき地震対策は?理由や対策の進め方まで徹底解説
2025/04/08
企業にとって、地震対策は避けて通れない課題の一つです。
しかし、多くの企業が「何から始めればよいのかわからない」「効果的な対策方法が見つからない」といった悩みを抱えています。
本記事では、企業が実施すべき地震対策について、オフィス内の具体的な対策から、実践的な防災訓練の方法、効果的なマニュアルの作成方法まで、実務に即した内容を解説します。
これらの対策を実施すれば、従業員の安全を確保するだけではなく、事業継続性を高め、取引先からの信頼獲得にもつながります。
どんな地震対策が必要なのか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
地震対策を行う企業の現状と課題
地震対策は、企業の存続に直結する要素の一つです。
自然災害が企業活動に与える影響は計り知れず、その準備の有無が、経営の安定性や競争力を左右します。
ここでは、企業に地震対策が求められる理由や現状を解説します。
地震対策が求められる理由と企業の現状
企業の地震対策は、事業継続の観点からみて経営の課題の一つと言えます。
なぜなら、地震による被害は企業活動のあらゆる面に影響を及ぼし、対策の有無が企業の存続を左右する可能性があるためです。
地震が企業に与える影響は、大きく直接的被害と間接的被害の2つに分類されます。
直接的被害には建物の倒壊や設備の損壊といった物的被害に加え、従業員の負傷などの人的被害が含まれます。
一方、間接的被害には事業停止による売上減少、取引先への納品遅延、市場シェアの低下などが挙げられるでしょう。
特に近年のビジネス環境では、サプライチェーンのグローバル化により、一企業の被災が取引先や関連企業に連鎖的な影響を及ぼすケースが増加しています。
また、従業員や来客の安全確保、帰宅困難者への対応など、企業としての社会的責任も従来以上に重視されるようになっています。
地震による企業への具体的な影響をまとめると、以下のとおりです。
| 直接的被害 |
|
|---|---|
| 間接的被害 |
|
| 社会的影響 |
|
これらの影響を最小限に抑え、企業としての社会的責任を果たすためにも、地震対策は経営における必須の取り組みと言えるでしょう。
対策の実施は、リスク管理としてだけではなく、企業の持続的な成長を支える経営基盤として捉える必要があります。
企業の地震対策実施状況と課題
多くの企業が地震対策の必要性を認識しながらも、実効性のある対策の実施には課題を抱えています。
特に中小企業では、具体的な取り組み方法や実施体制の構築に苦慮しているケースも多くあるのが現状です。
この背景には、防災・減災対策に関する知識や経験の不足、人材・予算の制約、さらには優先順位の低さなど、複数の要因が絡み合っています。対策を実施している企業でも、形式的な対応に留まり、実践的な効果が期待できない状況も少なくありません。
企業の地震対策での主な課題には、以下のようなものが挙げられます。
| 体制面の課題 |
|
|---|---|
| 実務面の課題 |
|
| 継続性の課題 |
|
これらの課題を解決するためには、経営層の積極的な関与と、段階的かつ計画的な取り組みが不可欠です。
特に、企業規模や業態に応じた実現可能な対策から着手し、継続的に改善していく姿勢が必要です。
地震対策がもたらす企業価値
適切な地震対策の実施は、災害時の被害軽減だけではなく、平常時からの企業価値向上に貢献します。これは、リスク管理体制の強化と社会的責任の遂行が、企業の持続的な成長に直結するためです。
実効性のある地震対策は、事業継続性の確保という直接的な効果に加え、従業員や取引先との信頼関係強化、社会的評価の向上など、多面的な価値を企業にもたらします。
また、対策の実施プロセスを通じて、組織の危機管理能力や従業員の防災意識も向上します。
地震対策による企業価値向上の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
| 事業継続性の強化 |
|
|---|---|
| 組織力の向上 |
|
| 企業競争力の強化 |
|
地震対策は、単なるコストや義務的な取り組みではなく、企業の持続的成長を支える経営投資として位置づける必要があります。
特に、従業員の安全確保や事業継続性の確保は、企業の社会的責任を果たすとともに、長期的な企業価値の向上につながります。
オフィスにおける具体的な地震対策
地震はいつ起こるか予測できないため、オフィスでの対策は欠かせません。
ここでは、オフィスの家具の固定方法や注意点、避難経路の見直し、そして防災備品の選定と配置について詳しく解説します。
オフィス家具・什器の固定方法と注意点
オフィス家具や什器の転倒・落下防止対策は、地震発生時の人的被害を防ぐための最も基本的かつ重要な対策です。
東京消防庁の調査によると、地震でのけがの約30~50%が家具類の転倒・落下・移動によるものとされています。
参照:東京消防局「地震時の危険」
オフィスには、キャビネットやロッカーなどの大型家具、コピー機などの重量機器が多数設置されています。
これらが地震で転倒・落下すると、深刻な人的被害をもたらす可能性があるため注意が必要です。また、避難経路を塞ぐことで、二次災害のリスクも高まります。
固定が必要な主な対象物には、以下のようなものがあります。
| オフィス家具 |
|
|---|---|
| OA機器 |
|
| その他 |
|
具体的な固定方法と注意点は、以下のとおりです。
| キャビネット・ロッカー |
|
|---|---|
| OA機器 |
|
什器の固定は、本来の機能を損なわない範囲で、かつ確実な効果が得られる方法を選択する必要があります。定期的な点検と、必要に応じた再固定も欠かせません。
避難経路の確保と定期的な見直し
避難経路の確保は、地震発生時に従業員の安全な避難を実現するための大切な対策です。
単に避難経路を設定するだけではなく、実際に使用可能な状態を維持し、定期的な見直しを行うことが不可欠です。
地震発生時は、パニック状態や停電、建物の損傷など、通常とは異なる状況下での避難を余儀なくされます。
そのため、普段から実効性のある避難経路を確保し、全従業員が把握していることが、迅速かつ安全な避難につながります。
避難経路確保の主なチェックポイントや見直しのポイントは、以下のとおりです。
| 避難経路確保のチェックポイント |
|
|---|---|
| 月次点検項目 |
|
| 季節による確認項目 |
|
避難経路の確保は、定期的な見直しと実地確認を通じて、実効性を高めていく必要があります。
特に、オフィスのレイアウト変更時や季節の変わり目には、必ず再確認を行うことが大切です。
防災備品の選定と配置
防災備品は、地震発生直後から復旧までの期間に、従業員の生命と安全を確保するために不可欠です。
適切な備品の選定と、実用的な配置計画が、その効果を左右します。
地震発生時は、電気・水道・ガスなどのライフラインが停止する可能性が高く、また救助や支援物資の到着までに時間を要する場合もあるでしょう。
そのため、最低3日分、できれば1週間分の備蓄品を用意し、適切に管理・配置する必要があります。
防災備品の選定や配置の内容をまとめると、以下のとおりです。
| 必要な防災備品リスト |
|
|---|---|
| 効果的な配置のポイント |
|
| 定期点検項目 |
|
防災備品の整備は、単に物を揃えるだけではなく、実際の災害時に確実に使用できる状態を維持しなければなりません。
定期的な点検と更新、そして従業員への周知を通じて、実効性のある防災備品管理を実現する必要があります。
効果的な地震対策を実現するための施策
実践的な防災訓練の実施方法
実践的な防災訓練は、地震発生時に従業員が適切な行動を取るための効果的な準備の一つです。
地震の発生時は、平常時とは全く異なる状況での即断即決が求められます。
そのため、さまざまな状況を想定した実践的な訓練を行うことで、実際の災害時でも冷静な対応が可能になるでしょう。
基本となる訓練には、以下の3つがあります。
| 避難訓練 |
|
|---|---|
| 消火訓練 | 消火器や消火栓の使い方を実践的に学べる訓練 |
| 安否確認訓練 | 災害用伝言ダイヤルや安否確認システムの使用方法を確認 |
これらの訓練をより効果的にするためには、状況設定の工夫が大切です。
抜き打ち訓練を取り入れたり、夜間や悪天候を想定したりすることで、現実的な対応力が身についていくでしょう。
訓練ではそれぞれの役割を明確にすることが大切です。
リーダーや情報伝達係、応急救護担当など、実際の災害時を想定した役割分担を決めておきましょう。
実践的な訓練は、定期的な実施と振り返りを通じて、その効果を高めていくことができます。
1年に2回以上の実施を目標に、計画的な訓練を心がけましょう。
防災マニュアルの作成と活用
防災マニュアルは、地震発生時の行動指針を示すためのツールです。
地震発生時は混乱が予想され、冷静な判断が難しくなります。
そのため、平常時に具体的な行動手順を定め、全従業員が理解しておくことが、迅速かつ適切な対応につながります。
効果的な防災マニュアルには、以下の3つの要素が必要です。
| 初動対応の明確化 |
|
|---|---|
| 役割と責任の明示 |
|
| 連絡体制の整備 | 緊急時の連絡手順を記載 |
防災マニュアルは作成して終わりではありません。
定期的な訓練で実効性を確認し、必要に応じて改訂を重ねることで、真に役立つツールとなります。
地震対策に役立つツールの導入
地震対策の実効性を高めるには、適切なツールの活用が不可欠です。
特に安否確認や情報共有を効率的に行うためのシステム導入は、企業の危機管理体制の改善に役立ちます。
地震発生時は、従業員の安否確認や情報収集、関係者との連絡など、多くの作業を同時に行う必要があります。
そのため、これらの業務を効率的に実行できるツールの導入が、迅速な対応につながります。
効果的な防災対策ツールには、以下のような機能が求められます。
| 安否確認システム |
|
|---|---|
| 情報共有機能 |
|
| 防災管理機能 |
|
例えば、総合防災アプリ「クロスゼロ」では、これらの機能を一つのプラットフォームで提供していて、気象情報と連携した自動安否確認や、組織内の円滑な情報共有を実現できます。
クロスゼロの主な機能には、以下のようなものが挙げられます。
- 安否確認(気象情報と連携した自動配信)
- 防災情報(リアルタイムな災害情報配信)
- 防災トリセツ(様々な災害に対する備え、発生時・避難時の知識・情報)
- 備蓄管理(備蓄品の在庫・期限管理)
- リスク共有(災害リスクの可視化)
- 掲示板(組織内の情報共有)
- チャット(緊急時のコミュニケーション)
- ファイル共有(重要書類の保管・共有)
- 家族機能(従業員家族との連絡手段)
- 災害モード(緊急時の特別機能)
クロスゼロの詳細を確認したい場合は、クロスゼロの公式サイトを確認してください。
防災ツールは、日常的な使用を通じて、その効果を発揮します。
導入後は、定期的な訓練での活用と従業員への使用方法の周知を心がけましょう。
まとめ
企業での地震対策は、従業員の安全確保と事業継続の両面から欠かせない取り組みです。
本記事では、企業が取り組むべき地震対策について、現状の課題から具体的な実施方法まで解説してきました。
地震対策の基本は、オフィス内の安全確保です。
オフィス家具の固定や避難経路の確保、防災備品の配置など、基本的な対策をしっかりと行う必要があります。
特に、家具類の転倒は地震によるけがの主な原因となっていて、適切な固定対策が人的被害の軽減に直結します。
また、対策の実効性を高めるためには、実践的な防災訓練の実施と、具体的な防災マニュアルの整備が不可欠です。
これらの対策をより効率的に進めるため、安否確認システムなどの防災対策ツールの活用も効果的です。
防災対策ツールとしておすすめなのが「クロスゼロ」です。
クロスゼロは、備蓄管理の他、災害発生時の安否確認やハザードマップや避難情報の機能で、避難行動をサポートします。災害時に役に立つでしょう。
地震対策は一朝一夕に完成するものではありませんが、できることから着実に実施していくことで、確実な防災体制を築いていけるでしょう。
クロスゼロは30日間無料で利用体験できます。会社の地震対策を行いたい方、見直したい方は、まずは30日間の無料体験で使い心地をお試しください。