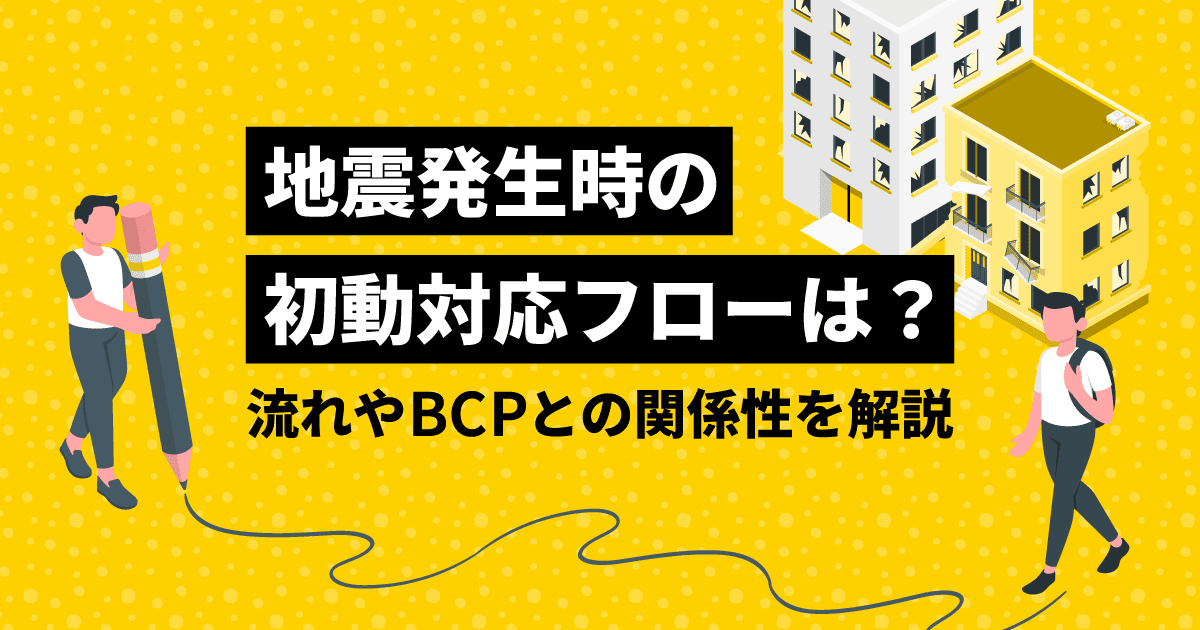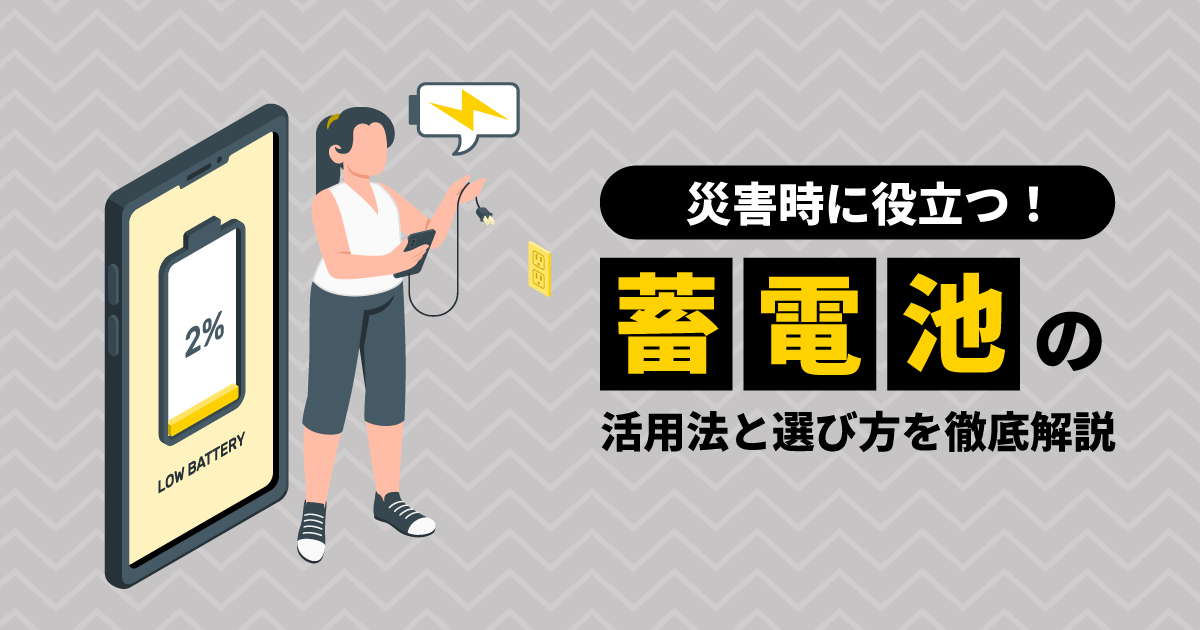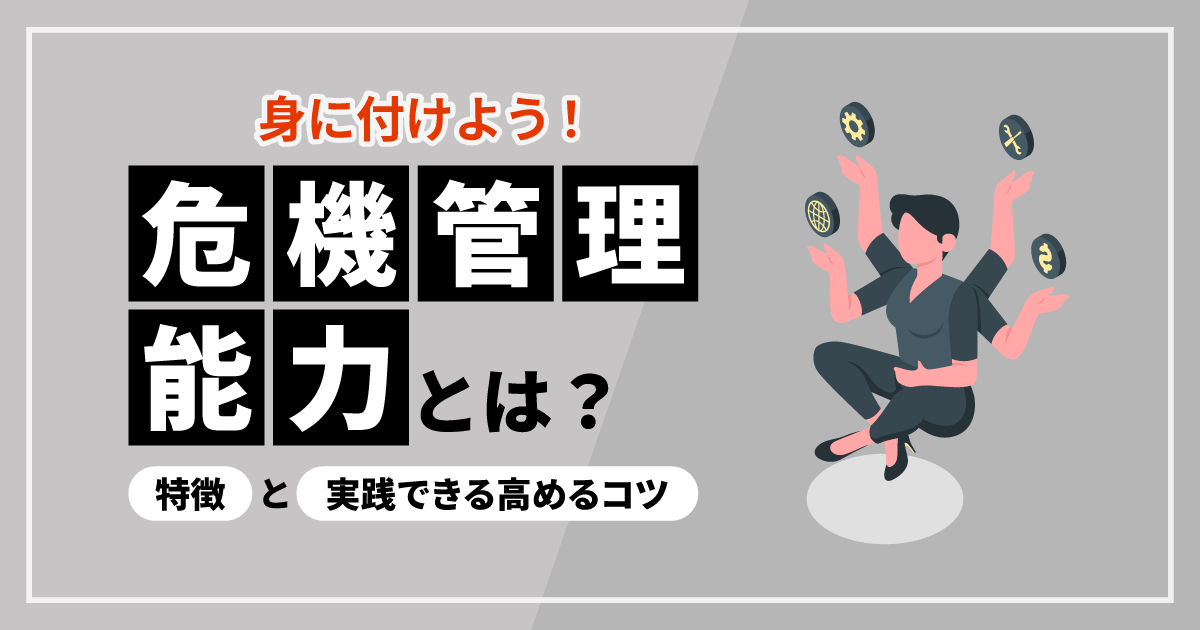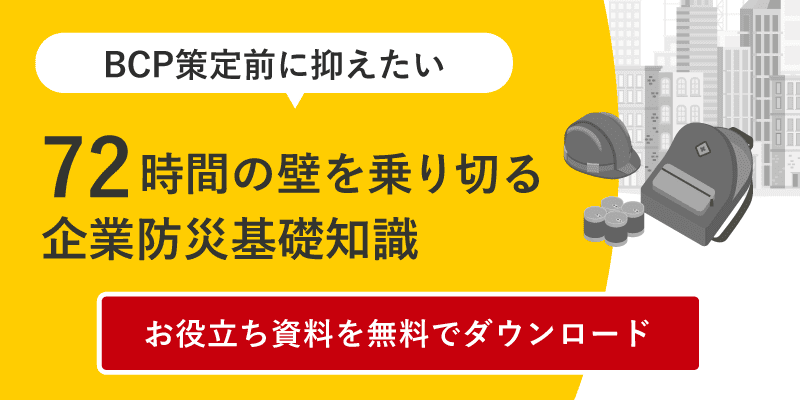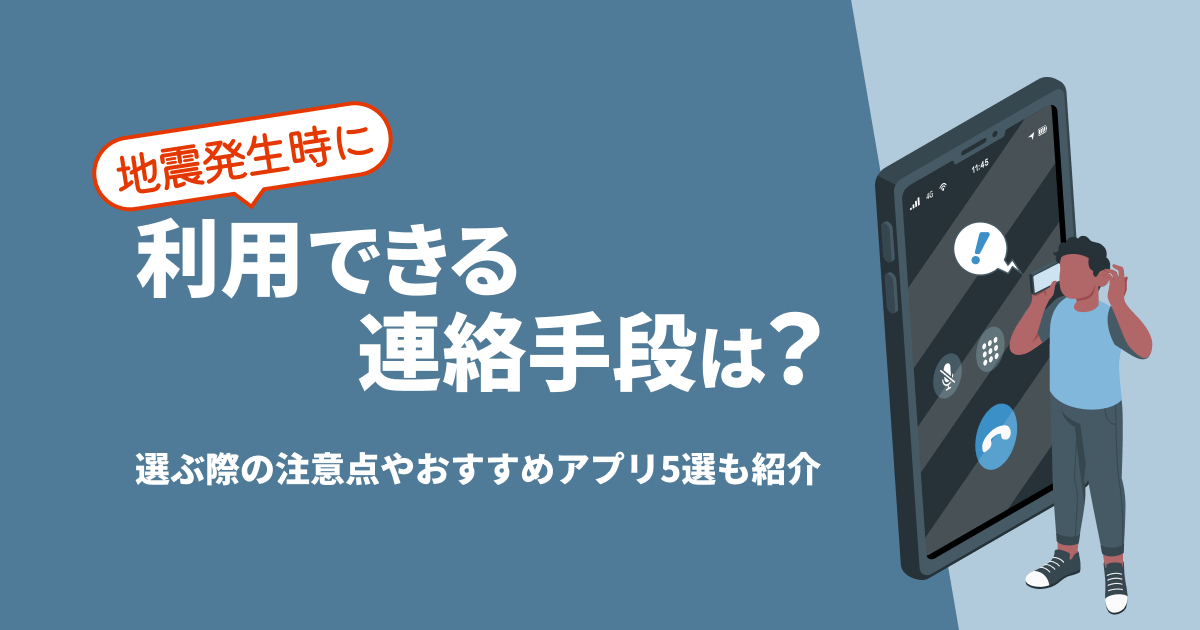
地震発生時に利用できる連絡手段は?選ぶ際の注意点やおすすめアプリ5選も紹介
2025/04/01
大規模な地震が発生すると、電話がつながりにくくなり、家族との連絡が取れなくなってしまいます。
実際、東日本大震災では多くの人が連絡手段の確保に苦労したと言われています。
しかし、災害時でも利用できる連絡手段はたくさんあります。
災害用伝言ダイヤルやWeb171、LINEの災害用伝言板など、状況に応じて使い分けることが可能です。
本記事では、地震発生時に使える具体的な連絡手段と、それぞれの特徴を詳しく解説します。災害時に役立つアプリも厳選して紹介しているので、いざという時の備えに活用してください。
家族との確実な連絡手段を確保するために、ぜひ参考にしてください。
地震発生時でも利用可能な連絡手段は?
地震発生時には、複数の連絡手段が利用できます。
ここでは以下の5つの連絡手段を紹介していきます。
それぞれの詳細を確認していきましょう。
災害用伝言ダイヤル(171)
大規模な地震が発生すると、電話回線が混雑して家族との連絡が取りづらくなります。そんな時に便利なのが、災害用伝言ダイヤル(171)です。
NTTが提供するこのサービスは、スマホや固定電話、公衆電話のいずれからも利用できます。スマホの充電が切れても、公衆電話からでも安否確認ができる点が特徴です。
災害用伝言ダイヤルの基本的な使い方は、以下のとおりです。
基本的な使い方
- 電話で「171」をダイヤル
- 録音か再生を選択⇒1:録音(暗証番号なし)2:再生(暗証番号なし)
- 被災地の方の電話番号を入力
- メッセージを録音(30秒以内)
費用について
- NTT電話サービス:無料
- 公衆電話:無料
- その他の通信会社:各社で料金が異なる
事前に準備しておくこと
- 家族共通の電話番号を決めておく
- 定期的に体験利用で使い方を確認する
- 公衆電話の設置場所を確認しておく
体験利用について <体験利用が可能な日時>
- 毎月1日:0:00~24:00(1月1日を除く)
- 正月3が日:1月1日0:00~1月3日24:00
- 防災週間:8月30日9:00~9月5日17:00
- 防災とボランティア週間:1月15日9:00~1月21日17:00
<体験利用時の条件>
- 録音可能な伝言数:20件
- 伝言の録音時間:30秒
- 保存期間:体験利用期間終了まで
NTT西日本「体験利用のご案内」
一般の電話回線が混み合う中でも、公衆電話からは比較的つながりやすいため、複数の連絡手段の一つとして覚えておきましょう。体験利用期間を活用して、家族全員が使い方を確認しておくことをおすすめします。
Web171(災害用伝言板)
Web171は、インターネットを使って災害時の安否確認ができるNTTのサービスです。
災害時、格安SIMユーザーは通常の災害用伝言板サービスを使えない場合があります。Web171は、キャリアに関係なく、スマホやパソコンから利用できる連絡手段として開発されました。
利用方法や主な内容は、以下のとおりです。
基本的な使い方 <伝言を登録する場合>
- Web171のサイト(www.web171.jp)にアクセス
- 電話番号を入力して「登録」をクリック
- 名前、安否情報、伝言を入力
- 「登録」で完了
<伝言を確認する場合>
- Web171のサイトへアクセス
- 確認したい電話番号を入力
- 「確認」をクリック
動作環境について
- 対応OS:Windows、macOS、Android、iOS
- 対応ブラウザ:Internet Explorer、Google Chrome、Firefox、Safari
体験利用期間
- 毎月1日・15日:0:00~24:00
- 正月三が日:1月1日0:00~1月3日24:00
- 防災週間:8月30日9:00~9月5日17:00
- 防災とボランティア週間:1月15日9:00~1月21日17:00
事前の準備として、Web171のサイトをブックマークに登録し、体験利用期間に一度操作を確認しておきましょう。
インターネット接続が可能な環境があれば、どの通信会社でも利用できる便利な連絡手段です。
LINEの安否確認
LINEには、災害時専用の安否確認機能が搭載されています。
日常的に使用しているアプリだからこそ、緊急時でも簡単に情報共有ができます。
大規模な地震が発生すると、一人ひとりに連絡を取ることは困難です。
LINEの安否確認機能を使えば、すべての友人・知人に一度で自分の状況を伝えられます。
LINEの災害時機能には、以下のようなものがあります。
| 安否確認機能 |
|
|---|---|
| 避難場所の共有 |
|
| 位置情報の送信 |
|
災害時、LINEは効果的な連絡手段となります。
普段から家族や友人とLINEでつながっておき、位置情報の送信方法も確認しておきましょう。
X(旧Twitter)
X(旧Twitter)は、リアルタイムで情報共有ができるSNSです。
この特徴を活かせば、災害時の情報収集にも活用できます。
大規模災害時には、地域の被害状況や交通情報など、さまざまな情報を素早く入手する必要があります。
Xでは、自治体や公的機関の公式アカウントをフォローしておくことで、正確な情報をタイムリーに受け取りやすくなるでしょう。
Xの活用法には、以下のようなものが挙げられます。
| リスト機能の活用方法 |
|
|---|---|
| フォローしておきたい情報源 |
|
Xのリアルタイム性を災害時に活かすためには、事前の準備が大切です。
自分の地域に関連するアカウントをフォローし、信頼できる情報源をチェックしておきましょう。
ただし、さまざまな情報が飛び交ってしまい欲しい情報がすぐ手に入らないというデメリットもあるため、公的機関の発信する情報を中心に確認するようにしてください。
災害用アプリ
スマホの機能を活かした災害用アプリも、効果的な連絡手段の一つです。
プッシュ通知や位置情報機能を使って、素早い情報共有が可能です。
災害時、電話やメールが使えない状況でも、専用アプリならインターネット経由で情報確認ができます。
家族の居場所確認や、避難所情報の確認など、さまざまな用途に対応しているため連絡手段の一つとして、ダウンロードしておくと便利でしょう。
災害用アプリでは、以下のようなことができます。
- 地震や気象情報の受け取り
- 家族との安否確認
- 避難所や給水所の地図表示
- オフラインでの情報確認
- 現在地周辺の災害情報
事前に災害用アプリをインストールしておくと、いざという時に慌てずに済みます。
普段から家族で使い方を確認し、実際の災害時にスムーズに活用できるよう準備しておきましょう。
各連絡手段のメリット・デメリット
地震発生時の連絡手段には、それぞれ特徴があります。
ここでは、各連絡手段のメリットとデメリットを比較してみましょう。
自分に合った連絡手段を選ぶ際の参考にしてください。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 災害用伝言ダイヤル(171) |
|
|
| Web171 |
|
|
| LINE安否確認 |
|
|
| X(旧Twitter) |
|
|
| 災害用アプリ |
|
|
このように、どの連絡手段にも一長一短があります。
災害時は、通信状況や電力状況によって使える手段が限られる可能性があるため、複数の連絡手段を用意しておくことが大切です。
家族で話し合い、普段から使い方を確認しておきましょう。
地震時の連絡手段を選ぶときの注意点
地震が発生した時、家族や大切な人との連絡手段を確保しておくことは大切です。
しかし、どの連絡手段を選べばよいのか迷う方も多いでしょう。
ここでは、地震時の連絡手段を選ぶ際の注意点を解説します。
複数の連絡手段を確保する
災害時は、一つの連絡手段だけでは不十分です。
状況に応じて使い分けられるよう、複数の手段を準備しておく必要があります。
地震発生時には、以下のように連絡手段が使えなくなる可能性があるため注意が必要です。
- 停電によるスマホの充電切れ
- 通信回線の混雑による電話のつながりにくさ
- インターネット回線の不通
- 携帯電話の基地局の損傷
例えば、スマホを主な連絡手段にしている場合、充電切れに備えて公衆電話の使い方も確認しておきましょう。
電話が繋がりにくい場合に備えてWeb171の使い方も覚えておくと安心です。
このように、異なる特徴を持つ連絡手段を組み合わせることで、災害時でも確実に連絡を取り合える可能性が高まります。
いざという時のために、家族でどのような連絡手段をどのように使うのか事前に話し合い、実際に試しておくと良いでしょう。
緊急時でも簡単に操作できるものを選ぶ
地震発生時は、強い揺れや停電、避難行動など、普段と異なる状況に直面します。
こういった災害時は、冷静な判断が難しくなります。
複雑な操作が必要な連絡手段は、パニック状態では使いこなせないかもしれません。普段から使い慣れた、シンプルな操作の連絡手段を選びましょう。
例えば、災害用伝言ダイヤル(171)は、音声ガイダンスに従って番号を押すだけで使えます。
LINEの災害用伝言板は、普段から使い慣れているアプリの機能なので、緊急時でも直感的に操作できるでしょう。
連絡手段を選ぶ際は、家族全員が簡単に使えるかどうかも重視してください。
いざという時のために、定期的に練習しておくことも大切です。
家族全員が使いこなせる手段にする
災害時の連絡手段は、高齢の方や子どもでも使いこなせる手段を選びましょう。
地震はいつ発生するか分かりません。
家族が離れ離れの時に起きる可能性も考え、誰もが確実に使える連絡手段を決めておく必要があります。
スマホが得意な人だけ、パソコンが使える人だけ、といった偏りがあると、いざという時に連絡が取れなくなってしまいます。
例えば、お子さんがいる家庭なら、学校の緊急連絡網と合わせて災害用伝言ダイヤルの使い方を練習しておくと良いでしょう。
高齢の方がいる家庭では、複雑な設定が不要な連絡手段を優先的に選ぶことをおすすめします。
家族みんなで定期的に使い方を確認し、実際に体験利用をしてみましょう。
普段から練習しておくことで、災害時でも落ち着いて使うことができます。
通信が制限されても使えるものを選ぶ
災害時は、通信サービスが制限されることがあります。オフラインでも使える連絡手段も必ず含めておきましょう。
大規模な地震が発生すると、通信会社は通信量を制限する場合があります。これは、緊急通報や重要な連絡を確保するための措置です。
そのため、LINEやWeb171など、オンラインでしか使えない連絡手段だけでは不十分です。
公衆電話は災害時優先電話として指定されており、一般の電話回線が混雑していても比較的つながりやすいとされています。
また、事前に家族で決めておいた集合場所に伝言を残すなど、オフラインでの連絡方法も検討しておくと安心です。
インターネットに頼らない連絡手段を最低1つは確保しておきましょう。
災害時でも確実に家族と連絡を取り合うための備えとなります。
地震時の連絡に役立つ災害用アプリおすすめ5選
スマホの普及により、災害時に役立つアプリも多く登場しています。
地震の情報をいち早く通知してくれるものから、家族の安否確認に特化したものまで、さまざまな機能を持つアプリがあります。
ここでは、特におすすめの防災アプリ5選を紹介します。
クロスゼロ|災害時の情報共有
災害に対する備えから発災後の避難行動まで、防災対策をワンストップで管理できる総合的な防災アプリです。
クロスゼロの概要は以下のとおりです。
| 運営会社 | 株式会社建設システム |
|---|---|
| 対応災害 | 地震、大雨など |
| 対応エリア | 登録拠点・現在地に基づくエリア |
| 利用料金 |
|
| 主な機能 |
|
防災に関するマニュアルや避難経路、緊急連絡先などを一元管理できる点が特徴です。
組織内や家庭内でデータを共有しやすく、災害への備えから発災後の行動までを総合的にサポートしてくれます。
30日間の無料体験ですべての機能を試すことができます。機能や無料体験の詳細は、クロスゼロ公式サイトをご確認ください。
クロスゼロ公式サイト
NHKニュース・防災|最新の災害情報と避難指示
NHKニュース・防災は、公共放送局NHKが提供する信頼性の高い防災情報アプリです。プッシュ通知機能で、地震や津波、大雨などの緊急情報をいち早く受け取ることができます。
災害時の正確な情報収集に役立つNHKニュース・防災アプリの概要は以下のとおりです。
| 提供元 | 日本放送協会(NHK) |
|---|---|
| 対応災害 | 地震、津波、大雨など |
| 対応エリア | 全国 |
| 利用料金 | 無料 |
| 主な機能 |
|
NHKの報道に基づく信頼性の高い情報を、プッシュ通知でいち早く受け取ることができます。データマップでは降雨量や地震のマグニチュードなど、詳細な情報も確認可能です。
災害への備えとして、まずはインストールして地域設定をしておきましょう。
NHKニュース・防災公式サイト
Yahoo!防災速報|緊急速報と避難情報
5,000万以上ダウンロードされている実績を持つYahoo!防災速報は、多彩な防災情報をタイムリーに届けてくれるアプリです。
Yahoo!防災速報の概要は以下のとおりです。
| 運営会社 | LINEヤフー株式会社 |
|---|---|
| 対応災害 | 地震、津波、土砂災害など |
| 対応エリア | 全国 |
| 利用料金 | 無料 |
| 主な機能 |
|
地震や津波の情報はもちろん、土砂災害や熱中症など二次災害の可能性まで通知してくれます。避難勧告や最寄りの避難所情報も確認できるため、迅速な避難行動をサポートしてくれます。
遠方の実家や友人の地域情報も登録できるため、大切な人の安否確認にも役立つでしょう。
Yahoo!防災速報公式サイト
ココダヨ|家族の位置情報
災害時の家族の安否確認に特化した位置情報共有アプリで、気象庁の速報と連動した自動安否確認機能が特徴です。
ココダヨの概要は、以下のとおりです。
| 運営会社 | 株式会社ゼネテック |
|---|---|
| 対応災害 | 地震、大雨など |
| 対応エリア | 全国 |
| 利用料金 |
料金プラン(自然災害のみ)
※無料版あり(一部機能制限) |
| 主な機能 |
|
気象庁からの災害速報を受けると自動で安否確認ボタンが表示され、家族の位置情報とともに無事を確認できます。
無料版でも災害時の安否確認やバッテリー残量確認が利用可能で、基本的な防災機能は十分に使えます。
位置情報の公開レベルも細かく設定できるため、プライバシーにも配慮されています。
ココダヨ公式サイト
トヨクモ|社員の安否確認
3,000社以上の導入実績を持つ、法人向けの安否確認システムで、シンプルな料金体系と充実した訓練サポートが特徴です。
トヨクモの概要は、以下のとおりです。
| 運営会社 | トヨクモ株式会社 |
|---|---|
| 対応災害 | 地震、大雨など |
| 対応エリア | 全国 |
| 利用料金 |
|
| 主な機能 |
|
企業の防災対策として、30日間の無料トライアルですべての機能を試すことができます。
定期的な防災訓練の実施や、訓練後の詳細なレポート提供により、組織全体の防災意識向上にも役立ちます。
まとめ
地震発生時、家族や大切な人との連絡手段を複数確保する必要があります。
災害用伝言ダイヤル(171)やWeb171、LINEの災害用伝言板、Xなど、複数の連絡手段を用意して、使い方を確認しておきましょう。
連絡手段を選ぶ際は、家族全員が使いこなせるものを選ぶことが大切です。
災害時は通信が制限されることもあるため、インターネットに依存しない手段も必ず含めておく必要があります。
スマホアプリを活用すれば、より確実な防災対策が可能です。
NHKニュース・防災やYahoo!防災速報で最新情報を入手したり、ココダヨで家族の位置情報を共有したりできます。
企業での導入を検討している場合は、「クロスゼロ」などの安否確認システムも検討してみてください。
いざという時のために、これらの連絡手段を家族や職場で確認し、定期的に使い方を練習しておきましょう。
日頃からの備えが、災害時の安全を守ることにつながります。
本記事で紹介したクロスゼロは、安否確認はもちろん、災害情報の通知や備蓄品の管理ができる機能も備えています。さらに、災害発生前に防災知識や対応マニュアルを共有できる「防災トリセツ」や「ファイル共有」機能があり、社員の防災教育や訓練も支援します。
また、クロスゼロをご利用中のユーザー様の家族を招待して、安否確認やチャットでの連絡ができる機能も搭載しているので、従業員だけでなくその家族の安全も守ることができます。
「クロスゼロ」なら、BCP資料・緊急連絡網・拠点シフトをアプリで常時共有。訓練から本番まで同じ導線で運用でき、“形骸化しないBCP”を実現します。
まずは試してみたい方へ。クロスゼロを30日間、無料で体験できます。
確認できます
- LINE、LINEのロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標または商標です。
- その他の社名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
クロスゼロに関する
無料相談(最大60分)
総合防災アプリ「クロスゼロ」にご興味をお持ちいただいた方は、お気軽にお申し込みください。
企業防災の仕組みづくりや防災DXに関するご相談はもちろん、ご希望がございましたら「クロスゼロ」の機能をご覧いただくこともできます。